ヘパーデン結節はなにが影響するのか
ヘパーデン結節は予防できるか

ヘパーデン結節は、原因がわからないところが最大の問題です。館林のたまい接骨院でも、原因は追及できないケガのひとつとして考えています。ですが、なにも手掛かりがないわけではありません。実はいくつかの手掛かりがあり、ここから推測できる部分は出てきます。
つまり、予防も一部ではあるもののできる可能性があるといえるでしょう。とても大事なポイントです。
いろいろな側面から考えてみますので、自分に当てはまるか考えてみてください。
遺伝と環境の問題
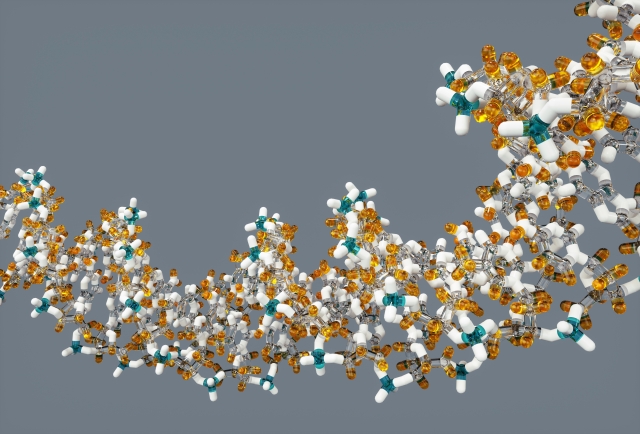
大前提として、遺伝性の問題があるかです。ここははっきりとわかっていません。遺伝は証明されていませんが、だからといって、否定できるだけの材料があるわけでもないからです。さらに家族内で複数発症するケースもあり、どうしても否定はできません。
もう一つの要因が、環境にあります。遺伝と混同して見られがちですが、家族であれば似たような生活になることが多いでしょう。食生活や生活リズムも似てきます。当たり前ですが、一緒に生活しているのであれば、当然なのです。これが影響している可能性はかなりあります。
その逆転的発想で、子どものころに、大豆食品などを多く摂取していると、発症しにくいとも言われてきました。つまり、環境的要因がヘパーデン結節につながる可能性があるのです。
加齢の問題も外せません。実は一定の年齢になると、指が曲がっているような手を見たことがありませんか?実はほとんどの人が結節を発症します。つまり珍しいものではないということです。
ここからわかるのは、女性ホルモンなどの変化が、影響しているのではないかということでしょう。エストロゲンの減少が、引き金になっている可能性が出てきます。
そうなると、どうしても女性に多く見られることがわかりますし、避けられないものであるということも考えなければいけません。
ヘパーデン結節の予防

いろいろな原因が考えられる中で、ヘパーデン結節の予防法も検討されてきています。使いすぎが影響するk脳性も指摘されているため、とにかく休む時間を作ることは大切でしょう。酷使しているだけで、関節に負担がかかるからです。
例えばPCをよく使っている人は、空き時間を作ること。編み物や裁縫も同様です。仕事で使っている場合には、オフのときはよく休ませてあげるだけで、将来への影響を下げられるのは確かです。
食事もできるだけ、大豆食品などを積極的に食べるよう、変化させていくのも予防に役立ちます。納豆だけでなく、味噌を使った料理などもありますし、投入もいいでしょう。
ちょっとしたことから始めるだけでも、将来の発症に対する予防に役立ってくれるからです。


